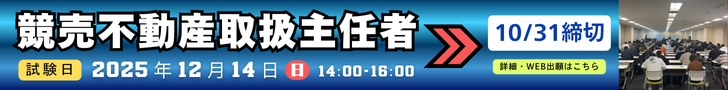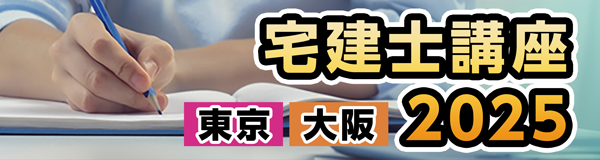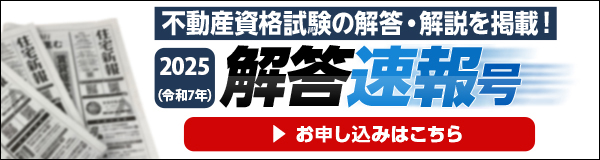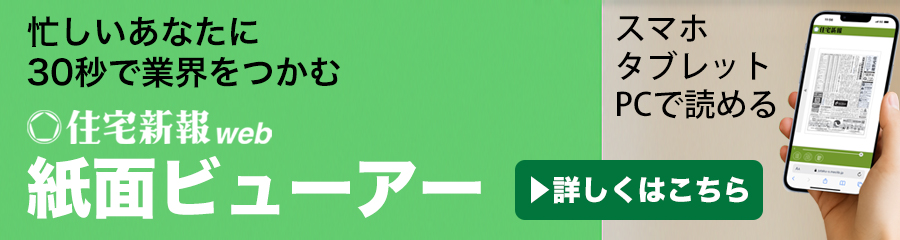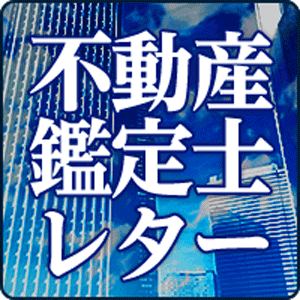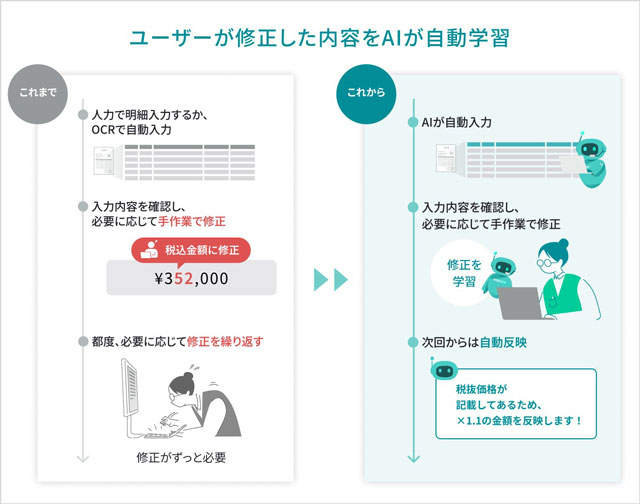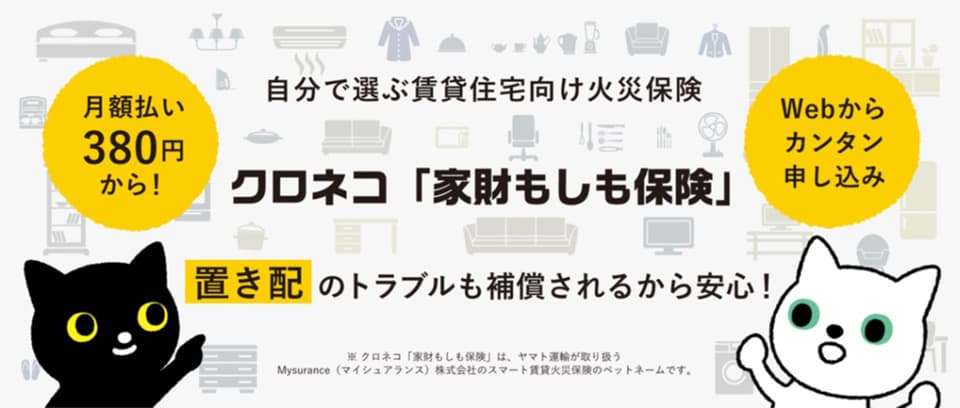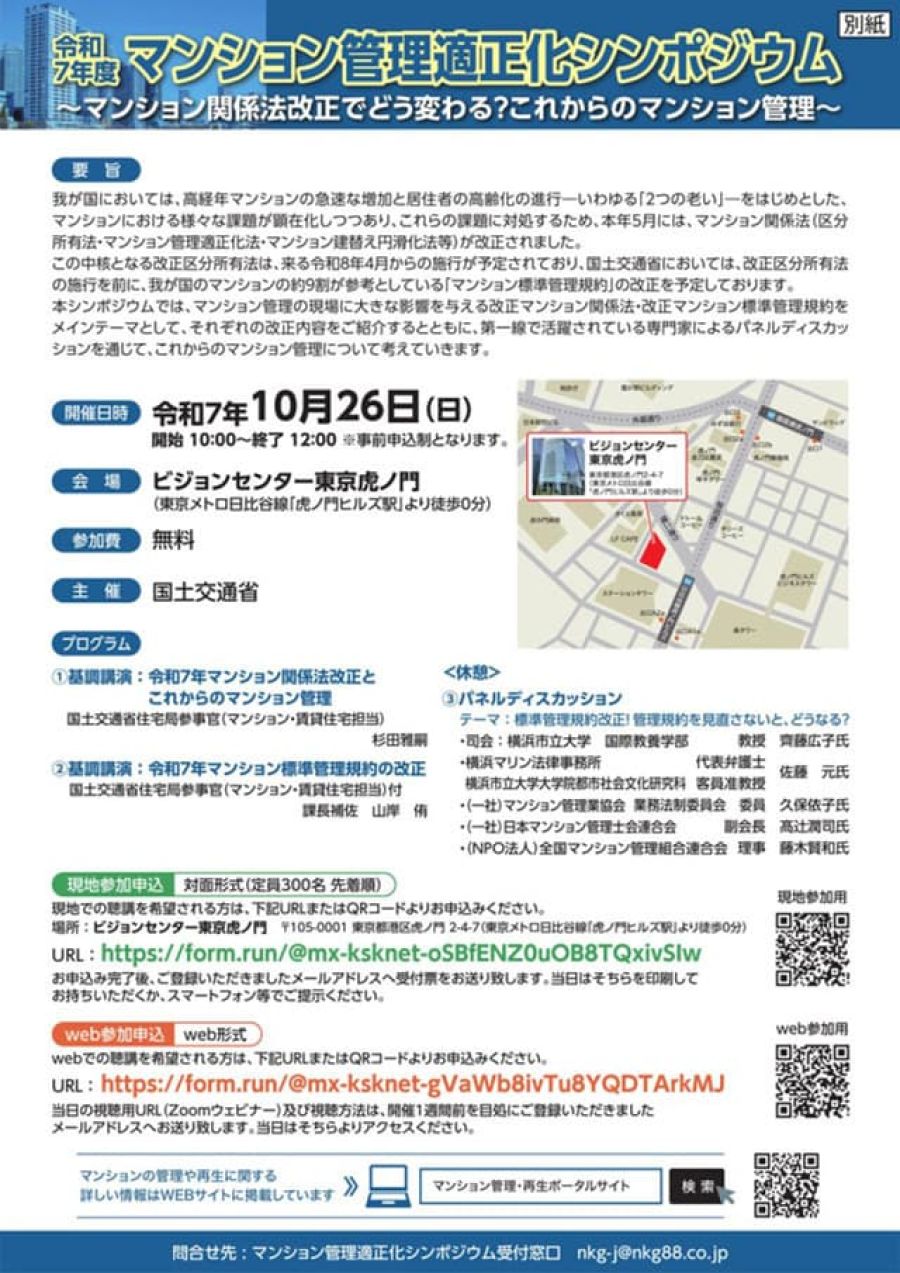不動産流通推進センターは5月1日、新雑誌『不動産コンサルティングプラス』を創刊した。空き家対策などを背景にコンサルティング業務に対する関心が高まりつつある今を好機と捉え、コンサル業務の更なる普及・発展を後押ししたいという強い意欲を感じさせる内容だ。
コンサル業務が従来の媒介業務とは一線を画し、国民の間で確たる存在となるための課題は2つある。一つは、媒介業務自体の〝コンサル化〟が進む今日、媒介とコンサルとの線引きは本当に可能なのかという問題。コンサルなしの媒介はありえない。
もう一つは、クライアントが大地主とか企業であれば報酬の受領も難しくないだろうが、例えば空き家所有者などの個人から媒介報酬とコンサル報酬の双方を受領できるかという問題だ。媒介とコンサル報酬の別建ては国交省が認めている。800万円以下の低廉な空き家の媒介報酬上限額を33万円まで引き上げる措置が導入されたのも、個人からのコンサル報酬受領が難しいがゆえの措置と見えなくもない。現にこの措置はそれなりに宅建業者のやる気を起こさせているようだ。
創刊号に掲載された「不動産コンサルティング事例」(36ページ)には、愛媛県不動産コンサルティング協会(竹内学理事長)が扱った事例が紹介されている。これは首都圏在住の高齢者から松山市内に所有する空き家売却を依頼されたことを機に、空き家の前面の市道が狭いために常態化していた渋滞問題をも同時に解決した高度なコンサル事例だ。
市道の拡幅や下水道問題への対応などで市との交渉を何度も重ねただけでなく、空き家の隣接地を買い増すなどしてコンサルティング協会会員を対象にした空き家の入札でも高額落札に成功している。
このように不動産コンサルティングは依頼者だけでなく、渋滞解消など地域住民にも貢献できる公益性の高い仕事につながることがある。だからこそ、その社会的評価(ステータス)の確立が求められているわけだが、高度なコンサル業務だからといって常に公的利益をもたらすとは限らない。
◎ ◎ ◎
では、課題として挙げたコンサル化が進む媒介業務との線引きはどう考えればいいのだろうか。
筆者はコンサルの本質は「誠意」と、それに対する「感謝」だと思う。媒介業務にこの2つがないとは言わないが、報酬に上限があるゆえにサービスの質を高めようにも限界がある。誠意を尽くし切れないジレンマともいうべきか。
もともと「報酬」には提供された役務(サービス)に対する感謝の思いが込められている。そこが単なる「手数料」とは異なる点である。賃貸借契約で2年ごとに徴収される更新事務「手数料」に感謝する人はいないだろう。
コンサルの本質を誠意と感謝と捉えれば、媒介業務との線引きは実務的なことではなく、「誠意の深さ」つまりコンプライアンスの問題であることがわかる。
真の誠意と感謝があれば報酬問題は自然解消する。財力ある依頼者からはたくさんもらい、資力に乏しい個人からは「感謝の気持」だけ受け取ればいいのではないか。
◇ ◇
不動産流通推進センターが不動産コンサルティング技能試験・登録制度を開始したのは1993年のこと。コンサル制度発足に際しては弁護士団体や税理士界からの強い抗議活動があった。
不動産コンサルでは法律や税務に関する相談が必須と見られたからだ。しかし、創刊号に寄稿した大阪府不動産コンサルティング協会会長の井勢敦史氏(45ページ)は「不動産コンサルは各士業の枠に収まらない全般を網羅する」ところにその特質があると述べている。だからこそ社会課題解決の力にもなりえている。
33年目を迎えたコンサル制度が今、社会から強い期待を寄せられているのもその点が広く理解されるようになったからだと思う。