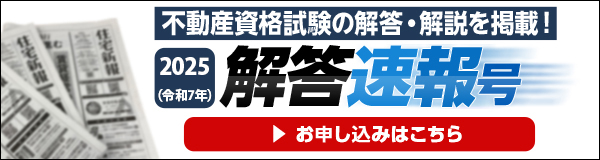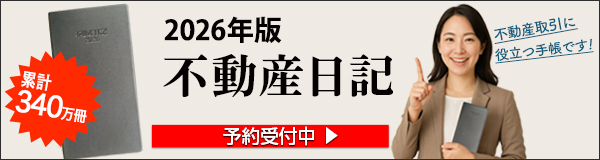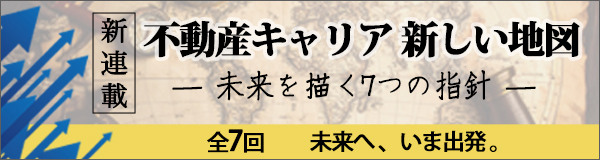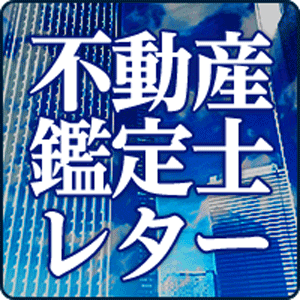「新たに建物をつくるのですが、建築に関係する都市計画法以外の法令や条例があったら教えてください」
都市計画課では都市計画法の各種都市計画制限を中心に建ぺい率、容積率などの説明を受けるのでそれを順にメモしていく。角地緩和など建ぺい率や風致地区など容積率の増減に影響する内容の説明があれば「どのように増減するのですか?」と詳細を確認していこう。
◎ ◎ ◎
これら基本的事項の確認が終われば、冒頭のようにその他の法令や条例も聞いていく。遠慮はいらず、何も考えず聞いていこう。都市計画課の窓口担当者は不動産会社慣れしているのか、またよく聞かれるためか、その他法令や条例も詳しいことが多い。分かっている範囲で教えてくれるので、聞いて確認する。
筆者も50歳過ぎだが新人のように聞いている。ベテランだからと言って思い違いして間違えるより100倍良い。答えは相手(都市計画課)が持っているのだから致し方がないと思って聞こう。
なお、不動産の流通量が多い市区町村役場の都市計画課だと各種法令や条例をどの窓口で確認ができるか、一覧表が置いてある。その場合は1枚もらい各窓口に行って聞くのがベストとなる。しかし、サービスの一環なのでない場合も多い。遠慮なく聞く習慣をつけておこう。
確認時には買主の購入目的に抵触する内容がないかをチェックする。該当するようなら窓口で「この都市計画道路内の建築制限を教えてください」と突っ込んでヒアリングを行う。「第53条の許可が必要ですので、こちらの建築なら可能です」など説明してくれるはずだ。もし、都市計画課で詳細が分からないなら「〇〇課(〇〇番窓口)で詳しく教えてもらえます」と案内はしてくれる。そうしたら、その窓口に向かい、聞いて確認をする。
その他法令や条例の詳細は関係する担当課や係があればその窓口で、それ以外は都市計画課で確認できることが多い。例えば、その他法令や条例において建築基準法や建築安全条例、がけ条例関係なら建築指導課、宅地造成等規制法は宅地課などが担当課だ。
条例は景観条例、建築安全条例、がけ条例、中高層関係条例(略称)、みどりの条例など複数ある。対象不動産と買主の購入目的に関係する条例はすべて内容も聞いておき、窓口かネットで詳細資料を入手し、どのように対象不動産に影響するかを把握する。
一通り話を聞き、確認ができたら最後にメモをチェック。漏れがなく、これで買主に説明できると自身で納得ができれば都市計画課の窓口は終了だ。続いて建築指導課か道路課の窓口へ進むことになる。
■ □ ■
【プロフィール】
はたなか・おさむ=不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。
2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。