地域連携型の管理の本領発揮が求められている――。国土交通省は9月、賃貸住宅管理業の今後のあり方を検討する議論を開始した。賃貸住宅管理業法の全面施行から丸4年、複雑化する業務と多様化する入居者ニーズを踏まえ、25年度内に見直しの方向性を示す計画だ。
主要論点は、(1)管理業務の見える化と報酬の明確化、(2)任意登録の促進、(3)業務管理者の資格要件の見直しと「賃貸不動産経営管理士」の社会的認知度向上、(4)地域連携型の管理強化である。登録業者が約1万社に達する一方、入居者の制度認知は低く、見直しの先に制度の普及促進を図らなければならない。
国は不動産業に対し、産業としての役割にとどまらず、地域資源である不動産を利活用し、他業種と連携してにぎわいを生み出す担い手として期待を寄せる。優良事例を称える「不動産業アワード」も整備され、中でも地域ストックと向き合う賃貸住宅管理業には、ステークホルダーとの接点の多さを生かした地域価値の共創が求められている。
ただし、個社の善意や個人の倫理観に依存しては持続性がない。仕組みづくりと周知徹底により、納得感の高い運用へと昇華させる必要がある。地域連携が深まれば、管理の守備範囲は広がるが、その効用は大きい。自治体・居住支援協議会・居住支援法人との連携により、住宅確保要配慮者への入居前相談から入居後フォローまでを一元化できる。多言語相談や子育て支援、退院・退所後の受け皿確保などの手順・窓口を標準化すれば、オーナーの不安は和らぎ、空室活用と入居促進につながる。更に、福祉・医療・警察・消防とのネットワークは、滞納・孤立・近隣紛争の兆候把握と早期解消を可能にし、見守りや緊急時対応を地域で担うことで、管理会社の個別負担とトラブルリスクを抑制できる。
一方で、当事者間の業務フローや責任範囲、連絡手段の明確化、協議会や居住支援法人の財源・インセンティブ設計、事務局の担い手確保、多機関連携の研修方法、地域格差の是正など、制度設計上の課題は多い。ここで鍵となるのがオープンな議論だ。失敗も含めて情報を共有し、データと事例に基づく是々非々の討議を通じて合意形成を進めたい。議論を業界内に閉じず、一般ユーザーの制度認知向上も視野に入れて透明性を高めることが、普及の近道となる。
その共通言語が賃貸住宅管理業法だ。同法を単なる順法チェックではなく、連携の土台として普及させ、協定や指標、研修に組み込む。国には、現場のリーダーシップを後押ししつつ、財源や人材・資格の確保を含む柔軟かつ大胆なフォローを求める。地域とつながり、議論を開き、制度を広める――この三位一体で、賃貸住宅管理業は地域の価値を高める中核へと進化できる。
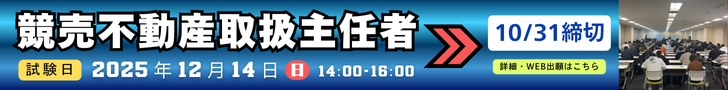
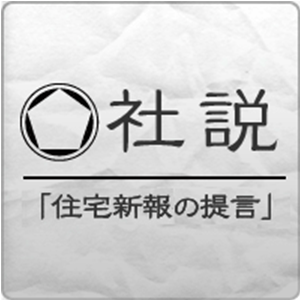





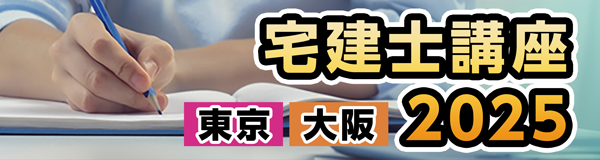
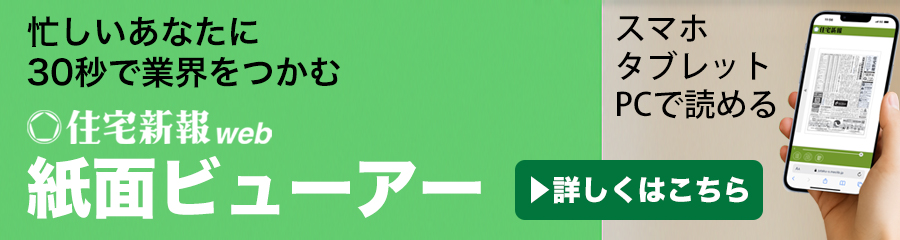


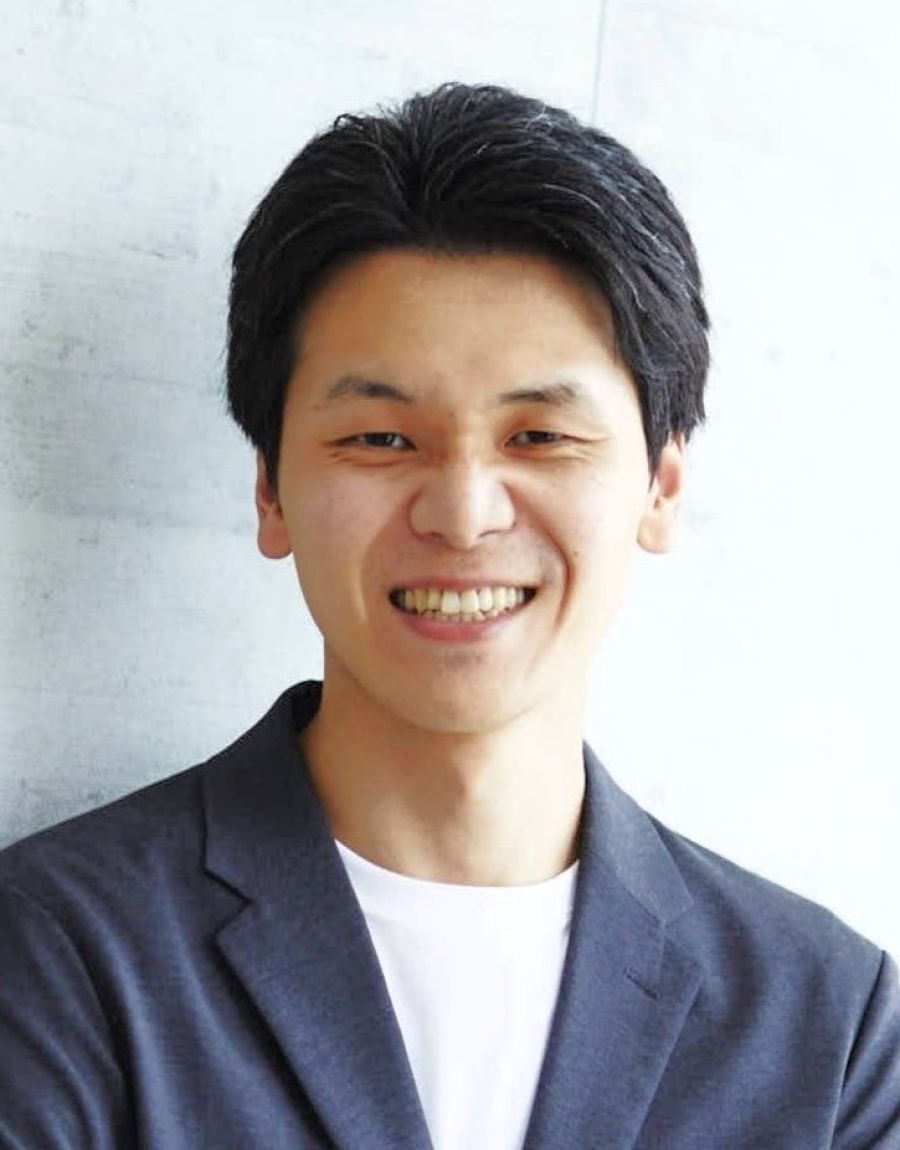





.jpg)
.jpg)

