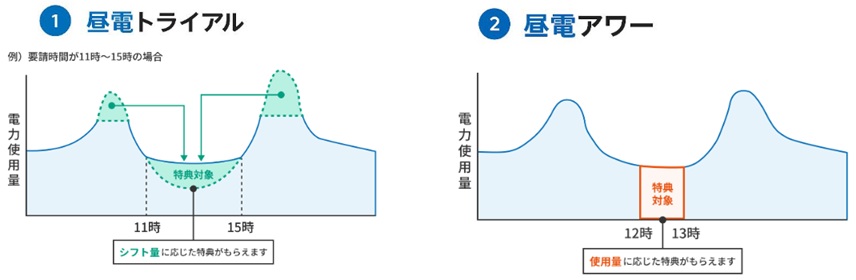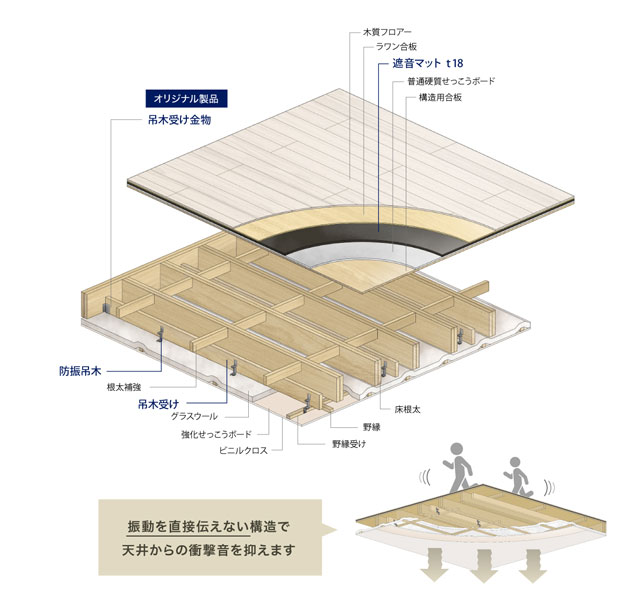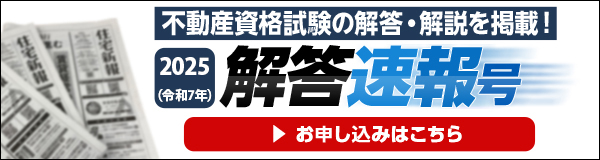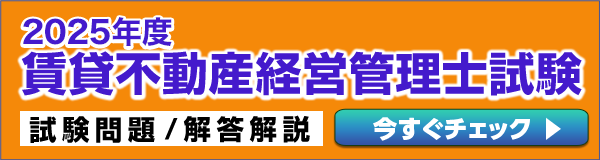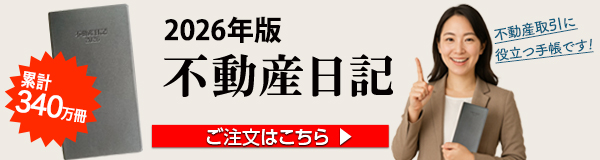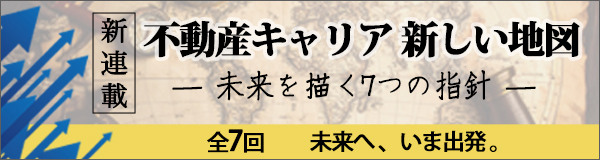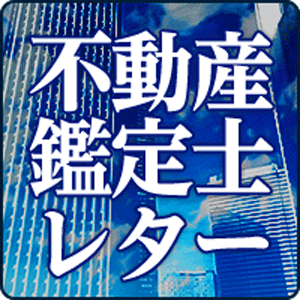普通借家権が存続する限り、定期借家権の普及拡大はおぼつかない。なぜなら普通借家権は1941(昭和16)年の正当事由制度導入以来、84年も続く賃貸借契約の脊柱となっているからである。事業者(仲介・管理会社)にとってはなんの違和感もないし最も習熟した事業スキームである。しかし、その常識もそろそろ見直すべきときである。
◇ ◇
分譲価格の高騰で住宅購入を足止めされた人たちが賃貸住宅市場にあふれている。一方、建築費や諸物価上昇を受け、オーナー(家主)は家賃の値上げを要請せざるを得なくなってきた。しかし、普通借家権は居住者(借り手)の保護を主眼としているため、簡単に値上げはできない。通常は管理会社が更新時に値上げ交渉を行うがすんなりと受け入れてくれる借り手は少ない。
オーナーが最も恐れるのは、このまま何年も値上げができないまま借り手が住み続けることだ。そのときになって、定期借家権にしておかなかったことを悔いても遅い。事業者も苦悩するオーナーを見て、ようやく定期借家権の必要性に気付き始めるのではないだろうか。
埋もれる魅力
定期借家権よりも8年早く創設された定期借地権は、普通借地権が制度としては併存しているものの、定期借地権創設以降はほとんどその活用実績がないため、徐々に定期借地権の魅力が理解されるようになり、今日の発展につながっている。定期借地も定期借家もその基本思想は同じなので、定期借家にも実はまだ理解されていない魅力が埋もれている。
その一つは契約期間がフリーであることだ。借地借家法第29条で普通借家権の契約期間は下限が1年以上と定められているが、定期借家権は下限も上限も規制はない。普通借家権も上限は自由だが、実際は「2年更新」が慣習となっている。改めて思うに、「2年」の根拠はどこにあるのだろうか。筆者は、住まいの契約としては短過ぎるように感じる。
定期借家契約なら慣習にとらわれず、借り手と協議し3年でも5年でも自在に定めることができる。今のように家賃が上昇傾向にあるときは、オーナーは短い期間にしたいかもしれないが、「住む場所」を貸すサービスであることを踏まえれば、5年程度までは承諾すべき期間ではないだろうか。少なくとも永遠に安い家賃のまま居座られる心配はないのだから。
個々の借り手のニーズに応じて契約期間を自在に決める慣習が生まれると、賃貸市場にはこれまでにない活気が生まれてくるように思う。期間が長くなれば賃料をディスカウントするケースも出てくるだろう。なぜなら、たとえ割り引いてもオーナーにとって契約した期間の賃料収益が確定するメリットは大きい(定期借家は期間中の賃料固定の特約が可能)。
一方、借り手にとっても落ち着いて(値上げの心配なく)住まい設計を立てることが出来る。例えば「子供が小学校生の間は転居しない」などだ。そういえば、最近の通販の広告では「通常価格○○円のところ、今回に限り○○円に割引」という常套句(じょうとうく)が出てくるが、通常価格で販売した実績があるのか怪しいものだ。その点、定期借家による割引は普通借家という通常(相場)賃料が周辺もしくは隣住戸にもあるのだから、そのインパクトは大きい。
◇ ◇
定期借家契約は地主など旧来のオーナーに限らず、今後一段と増えそうなサラリーマン(個人)投資家にとっても魅力だ。賃料収益確定のメリットも大きいが、家賃滞納、クレーマーなどの懸念が少しでもある借り手は契約期間を1年未満にして〝試行期間〟とすることができる。一般の居住者にとっても全戸定期借家契約の賃貸住宅であれば不良入居者を追い出すことができ、そうした機能をもつことこそが集合住宅にとっては究極の価値となる。