国会では食料品に対する消費税非課税化が物価高対策として大きな争点となっている。生活必需品である食料品の消費税率をゼロにすることで家計への負担を軽くするのが狙いだ。ただ、日本には「衣食住足りて礼節を知る」ということわざがあるように「食」が日々の糧(かて)なら、「住」も生きていくうえで欠かせない生活基盤である。現に家賃が非課税となっているのはそのためだ。にもかかわらず、同じ「住」なのに新築住宅の取得に際し建物部分が課税されているのはなぜか。
◇ ◇
国の考え方として「居住用賃貸の家賃は生活費の一部だが、住宅購入は資産形成行為」と見ていることが大きな理由とされている。しかし、持ち家もその後長い期間にわたって消費されていく耐久消費財である。また賃貸に住む人が低所得層で持ち家取得者は裕福層という考え方も影響しているとすれば時代錯誤もはなはだしい。むしろ逆である。だから富裕層が家賃何百万円もする高級賃貸に住んでも家賃は非課税、その一方で庶民がローンを組み生活費を削ってでも購入する住宅には建物部分に10%も課税という矛盾を生じることになる。
かつてはこうした点をめぐって政策論議が行われたこともある。「住宅取得は長期消費であり、一括課税は過重負担」「賃貸が非課税なのに購入が課税されるのは税制としての整合性を欠く」「食料品に軽減税率を導入するなら、住宅にも軽減措置を設けるべき」等々。
これに対し、政府は「住宅は所得階層によって取得額の差が大きい。そのため一律の軽減税率は高所得者に有利になりやすい」と主張していた。取得額に大きな開きがあることは今も事実だし、近年は生活基盤というよりも生活拠点としてセカンドハウスをいくつも所有したり、リゾート地のコンドミニアム型ホテルに投資するなどマルチハビテーション型の生活を楽しむ富裕層が増えている。それに比べると一般庶民にとっての持家は悲しいほど生活の基盤であり、生活の精神的支えともなっている。
不動産業界はそのことを再認識し、富裕層有利はさしおいても住宅取得についての住宅消費税軽減化を強く要望すべきである。あるいは所得制限を設ける方法もある。現にヨーロッパ諸国では住宅は資産形成というより「社会インフラ」更には「基本的人権の一つ」という思想から軽減税率を導入している。例えば以下の通りだ(カッコ内は標準税率)。
フランス=5.5%または10%(20%)、イギリス=0%または5%(20%)、イタリア=初めての住宅4%、2番目以降は10%(22%)、スペイン=一般住宅10%、公的住宅4%(21%)。
唯一の対応
住宅購入に対する消費税の非課税化は、現在の住宅価格高騰に対する唯一の対応措置にもなる。なぜなら、現在の価格高騰の要因となっている建築費高騰は依然続いており、頭打ちもしくは下がり始める様子が一向に見えてこないからである。
都内の新築マンション市場では1億円どころか2億、3億円以上のマンションが〝億ション〟として一般化しつつある。もし、2億円のマンションのうち建物価格が1億円なら消費税はなんと1000万円にもなる。
◎ ◎
ちなみに、東京23区の新築マンションにおける土地代と建物代の割合は一般的な目安として、都心区が70対30~60対40、城南・城西エリアが55対45、城東・城北が50対50~40対60と言われている。
今や一般勤労者世帯は中古マンション市場に選択肢を求めるしかないと言われているが、その中古市場でも消費税の軽減化は有効である。
中古住宅取引では売主と買主個人間の売買には消費税がかからないが、事業者が売主となる場合は課税されているからだ。また購入後のリフォームも非課税となれば中古市場の活性化につながっていく。








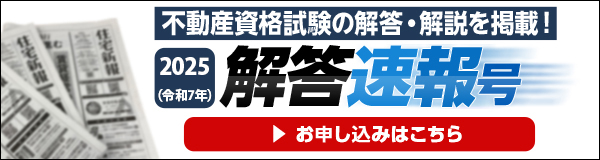
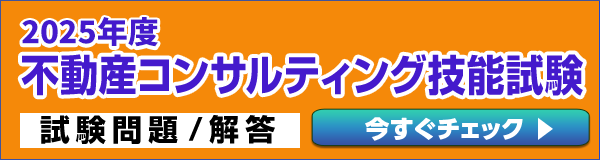
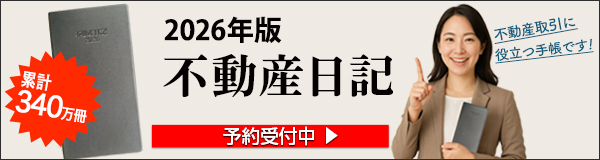
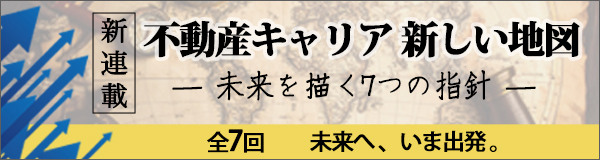









.jpg)

