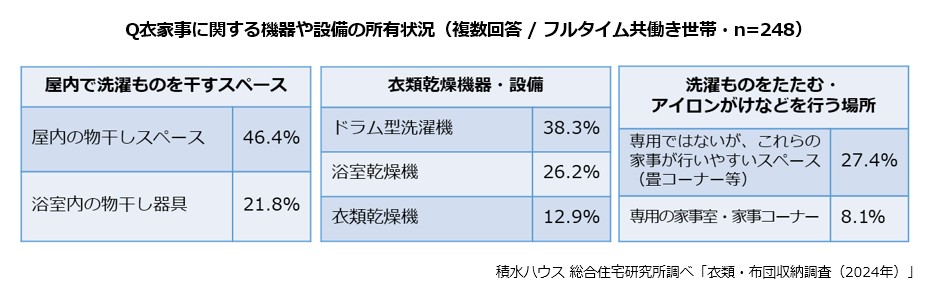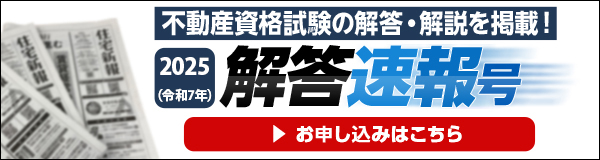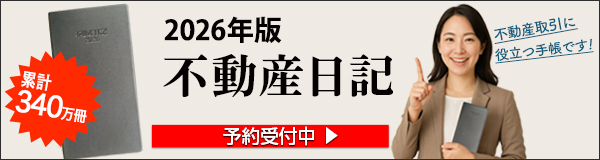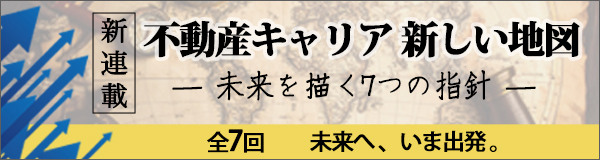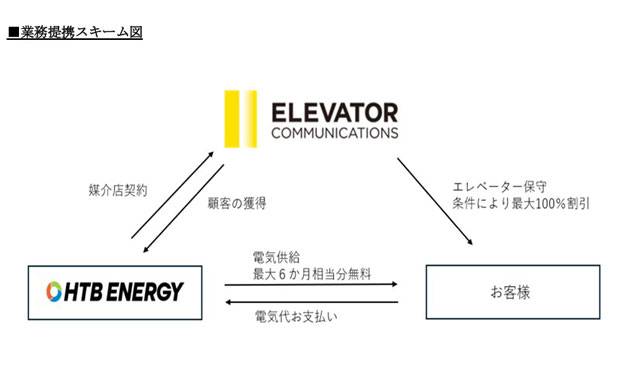あるエコノミストは「経済現象の7割は人口減少で説明がつく」と言う。
では、いっこうに止まらない人口減少はどう説明すればいいのだろうか。人口減少が今や先進国共通の世界的傾向となっていることから考えれば、それは明らかに、男女間の愛の変質と言わざるを得ない。「本能的愛から打算的愛へ」の変貌である。
◇ ◇
国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば日本の総人口は2025年の約1億2300万人から50年後の2075年には約8735万人まで減少する。減少数は約3600万人(約30%)で1年間に平均70万人以上の減少が続く。ただし、都市別に見れば人口が増えている都市もある。20政令市と東京23区で見ると、20年から24年までの推移で人口が増加していたのは以下の6都市となる。
(1)東京23区11万4968人、(2)福岡市4万4345人、(3)大阪市3万9495人、(4)さいたま市2万7111人、(5)川崎市1万3526人、(6)千葉市9647人(以上総務省統計局)。
日本全体の人口が減少していることを踏まえれば、これら都市の増加要因は自然増というよりも他の都市からの人口流入(社会増)が大きいと思われる。悪く言えば人口の奪い合いが行われているわけだが、自治体同士が人口増加に向け競い合うことは悪いことではない。互いに様々な政策を打ち出していくことで、いつの日か、社会増ではなく自然増につなげることができるかもしれないからだ。その意味でも、自治体にとっては首長の質とレベルが重要となってくる。
宅建業者がゼロ?
人口減少の波紋は当然、不動産業界にとっても大きい。地方では所有者不明土地や誰も欲しがらない〝負動産〟が増えているという。そのせいだろうか。国土交通省によれば現在、全国1747の市区町村のうち、247自治体(約14%)で宅地建物取引業者(宅建業者)の店舗が1軒も存在していないという(具体的市区町村名は非公表)。商売が成り立たなくなって廃業したのか、それとも他の地域に移転したのかは不明だが〝不動産業者ゼロ地帯〟が今後増加していくことは必至とも思われる。
商売が成り立たなくなったエリアの不動産業者が近隣の都市部に移転するケースが増えれば、都市部での業者間競争(顧客奪い合い)がいっそう激しくなるのは必然だ。参入組も迎え撃つ側も人口減でパイの縮小が続く中での競合となる。従来型の古いビジネスモデルのままで生き残れるとはとても思えない。首長に限らず、これからの宅建業者にも〝変革〟が求められている。
意識の時代
人口は減少しても人々の住まいに対する質的なニーズが深まっているという見方に立てばチャンスはあるし、新たなビジネスヒントも。ある不動産会社の経営者は言う。「会社の前に、道行く人たちのためにベンチを置いただけでも何かが変わる」と。
アールシーコアの創業者である故二木浩三氏は「情報化時代の次にやってくるのは〝意識の時代〟」ということを指摘していた。筆者なりに解釈すれば、人間にとっては意識がすべてであるから、「意識の時代」とはほかでもない「人間の時代」ということだろう。
◇ ◇
男女間の愛が本能的愛から打算的愛に変貌したのも、意識が働いて本能を変えたのである。二木氏は〝無意識〟についてもよく言及していた。「無意識でも行動に表れるとそれは意識である。そこに注目するのが感性マーケットだ」と。つまり意識の時代のビジネスヒントは〝感性〟だと二木氏は指摘していたのだと思う。
道にベンチが置かれていれば、人は置いた人の感性と好意に意識を向ける。人口減少という負の時代でも、世の中を豊かにするものがあるとすれば、それは人間が互いの存在に意識を向ける人としての感性を磨くことではないだろうか。