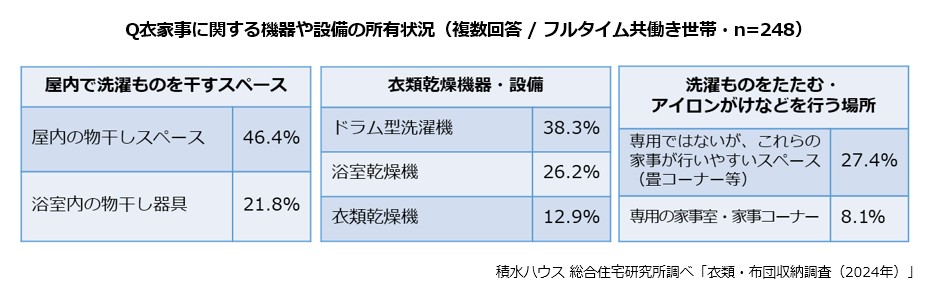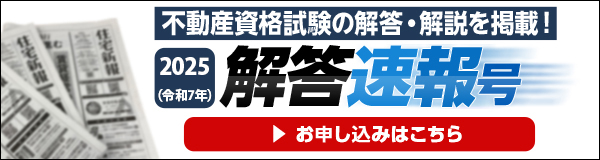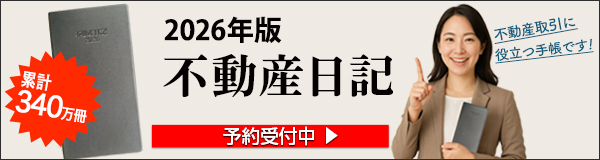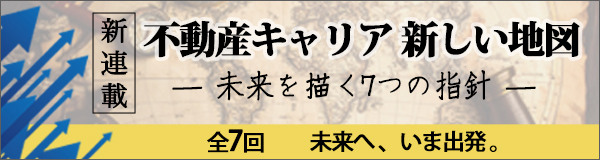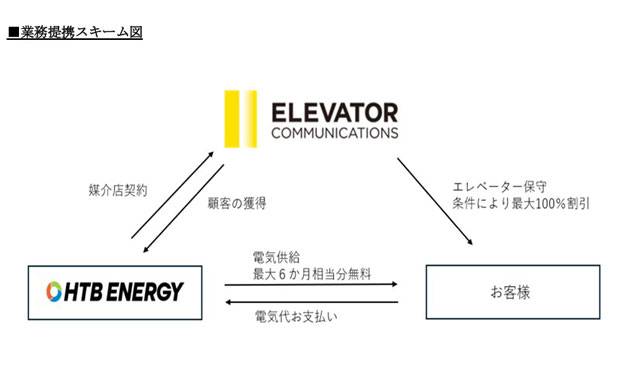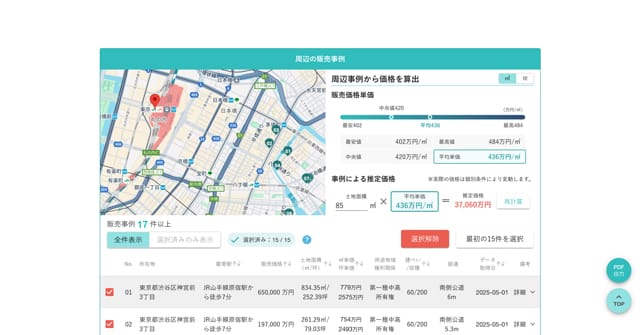長寿化が慶賀とは限らない。寿命が伸びても体の中の一部の機能はそれに追いつけず劣化し様々な支障(病気)を起こすケースが増えているからだ。認知症や脳梗塞(脳)、白内障や緑内障(眼)、難聴(耳)、骨粗しょう症(骨)などがその代表だろうか。平均寿命と健康寿命の差(男女とも約10年)がなかなか縮まらないのはそのためだ。 ◇ ◇
では、長寿社会を明るく楽しいものにするにはどうすればいいのだろうか。高齢者の衰えた身体機能をケアする様々な高齢者施設が地域に増え、住民にとってポピュラーになり、誰もが気軽に支えたり支えられたりする社会の実現が欠かせない。なぜなら、誰もがいずれは老いて体の機能の衰えに愕然とし、誰かのケアを受けなければならなくなるからだ。しかし、日本では今でも「親を施設に入居させるのは、どうも」という意識がある。本人が強く抵抗するケースも多い。こうした状況を改善するためにはサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホームなどの施設自体を大きく変革していくしかない(サ高住は施設ではなく賃貸住宅ではあるが実態は施設に近い)。
幸せ社会
〝施設〟に対する偏見で最も多いのが周囲(地域)から隔絶されているという印象だ。実際、特養など高齢者が出入りしているところを見たことがない施設が多いように感じる。そうした中、「地域との輪、さまざまな人との輪」をコンセプトにしたヘルスケアコミュニティ「Tonowa Garden 目白台」が7月7日、文京区の講談社裏手の高台にあった東京大学医学部付属病院分院跡地に誕生した。
三菱地所レジデンスが事業主になり、三菱地所の総合企画で複合建物賃貸事業を目的とする一般定期借地権契約を東京大学と締結した。期間は65年。サ高住、介護付き有老ホーム、クリニック、リハビリ特化型デイサービス、看護ステーション、コミュニティラウンジ、学童保育施設など多様な施設が併設されている。特に注目すべきはヘルスケアの研究機関である東京大学大学院医学系研究科付属の「グローバル ナーシング リサーチセンター(GNRC)」が併設されたことだ。人生100年時代の〝幸せ社会〟はどうすれば実現するかを研究していく拠点となる。同センター長の山本則子氏は「学校には必ず保健室があったように〝暮らしの保健室〟という役割も果たしていく」と話す。
進化するケア
もしかすると、ここ「Tonowa Garden 目白台」は、将来的には日本版CCRC(継続的ケア付き高齢者コミュニティ=Continuing Care Retirement Community)に成長していく可能性も秘めている。CCRC本場のアメリカではスタンフォード大学など有名大学のキャンパスの敷地内にシニアコミュニティが設営されることが珍しくないからだ。大学の卒業生や元教員など高学歴の高齢者が多いという。日本でも大学の知的資源と連携して「健康寿命延伸」や「生涯活躍社会」を目指す大学連携型CCRCは増え始めている。
◇ ◇
かつては高齢者施設といえば北欧諸国(スウェーデン、デンマークなど)が先進国と言われていたが、今では日本が世界の最先端を進んでいるという話も聞く。確かに日本は 高齢者施設の数・種類・テクノロジー活用の面では世界的にも進んでいるが、「自立を促す」という思想・ソフト面では依然として北欧には負けているように思う。実際、施設に入居すると、厚いケアのためにかえって要介護度が増したという話は多い。ある介護事業経営者は「自立を促し、要介護度を下げても利益にはならない」と苦笑する。この矛盾は大きい。
東大という我が国最高峰の大学の敷地内に誕生した新型ケアコミュニティの今後の進化に期待したい。