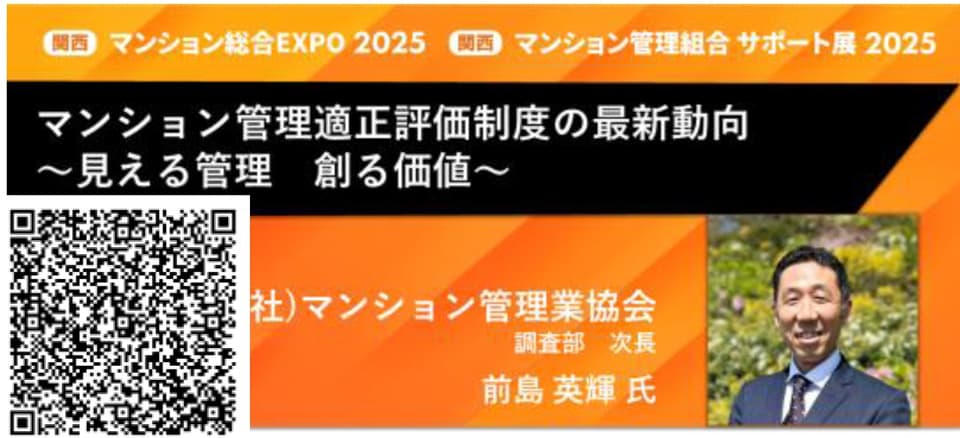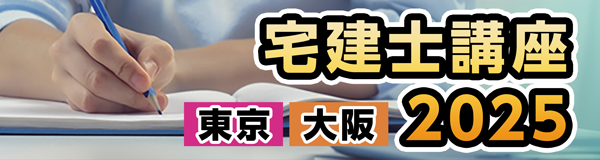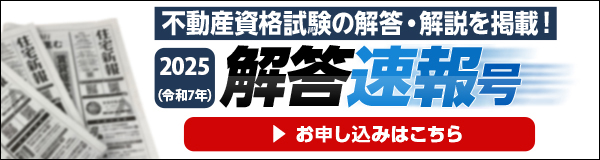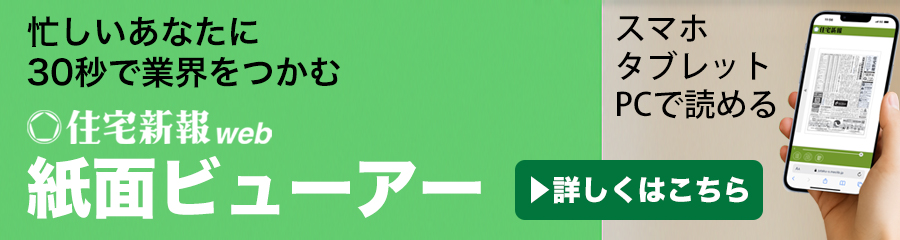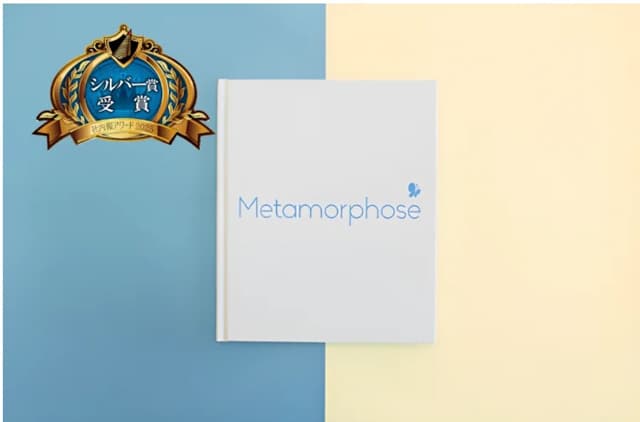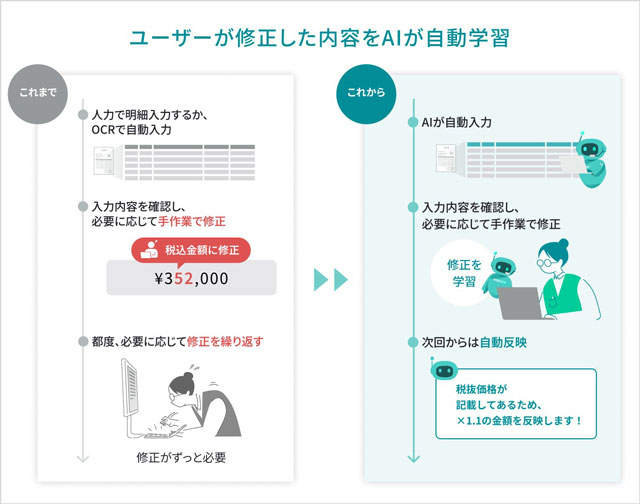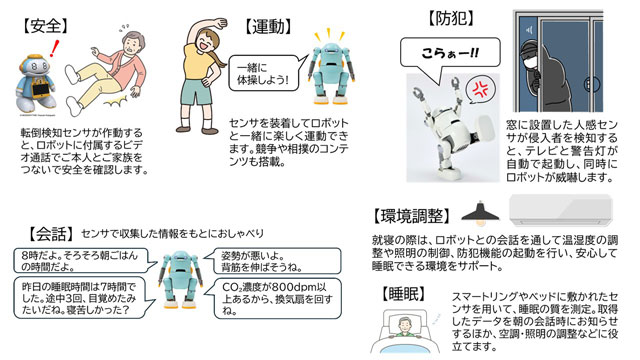建物表題登記は買主の金銭消費貸借契約(以降、金消契約)前に完了するか確認をする。買主には早めに登記申請を促して確認しよう。
建物表題登記とは新たに建物を建てたときに、建物の所在地や種類、構造、面積などを法務局に申請をして登記をすること。実務では注文や建売を問わず新築住宅の場合に、建物は未登記のため、この建物表題登記を行う。土地家屋調査士に買主(申請者)の委任状と住民票を用意した上で依頼し、法務局に申請し登記をする。建物表題登記の後には司法書士に保存登記を依頼し所有者を明確にする。
建物表題登記をしておかないと建物は未登記のままとなる。それでは銀行などの金融機関は抵当権を付けられない(担保に取れない)ので、ローンの実行はできなくなる。そのため私たちも「残代金決済時までには建物表題登記をしておかないといけないな」と分かりやすい。
ただ建物表題登記にはもう1つ重要なことがある。それは「家屋番号の確定」となる。土地家屋調査士が用意をした委任状に家屋番号が書かれているのを見つけてそれを信用していると、後で異なる家屋番号となる可能性もあるので注意が必要だ。登記が完了するまでは家屋番号は確定しない。土地家屋調査士が法務局に聞いて委任状等に家屋番号を記載するのだが、登記官がざっと調べて「この番号辺りにするか。同じ番号とかあれば申請があったら変えよう」(筆者推測)との仮番みたいなもので確定ではないようだ。土地家屋調査士に確認しても「ほぼこの家屋番号になりますが、正式な家屋番号は登記完了時に分かります」と言われてしまう。
この家屋番号で問題になるのが金消契約だ。契約書に担保となる不動産の家屋番号の記載が必要になるからだ。
金消契約時に分からなくても後で追記したり、訂正すれば良いじゃないか、買主(借主)は捨印するのだから追記も訂正は簡単だろうと甘く考えがちだ。筆者もそうだった。ただ稀(まれ)に金融機関から「システム上金消契約前に分からないとダメです」、「金消契約内容をPCで入力しますが、家屋番号が分からないとエラーが出るので早めにお願いします」などと言われ慌てることがある。そうならないように金消契約前、できれば金消契約の1週間前ぐらいには登記完了し家屋番号を確定としたほうが無難だ。
建物表題登記は申請から登記完了まで1~2週間掛かるとすれば金消契約の3週間前までには登記申請としたい。金消契約から残代金決済まで2週間とするなら、逆算して残代金決済の4週間から5週間前までに建物表題登記の申請を行おう。この辺りのスケジュール感は買主に伝えて手続きを進めていくと余計なトラブルとならず良いだろう。
◇ ◆ ◇
【プロフィール】
はたなか・おさむ不動産コンサルタント/武蔵野不動産相談室(株)代表取締役。2008年より相続や債務に絡んだ不動産コンサルタントとして活動している。全宅連のキャリアパーソン講座、神奈川宅建ビジネススクール、宅建登録実務講習の講師などを務めた。著書には約8万部のロングセラーとなった『不動産の基本を学ぶ』(かんき出版)、『家を売る人買う人の手続きが分かる本』(同)、『不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社)など7冊。テキストは『全宅連キャリアパーソン講座テキスト』(建築資料研究社)など。