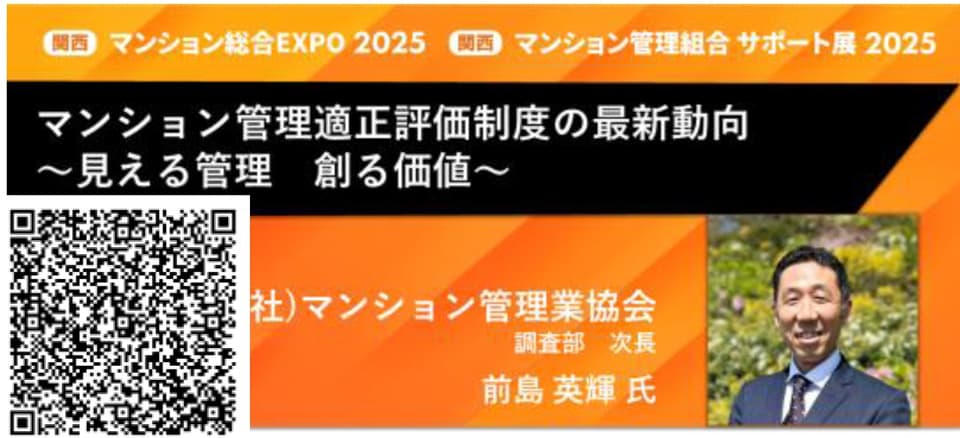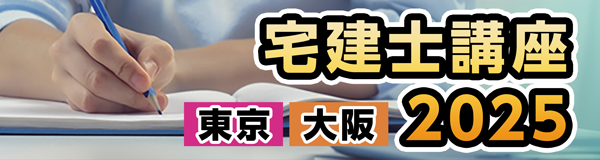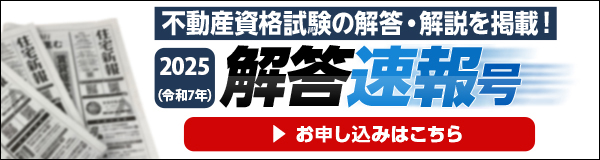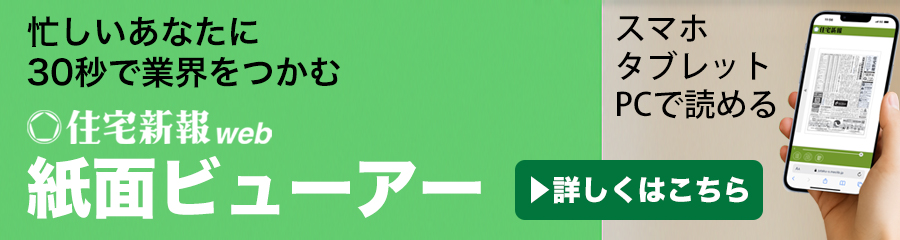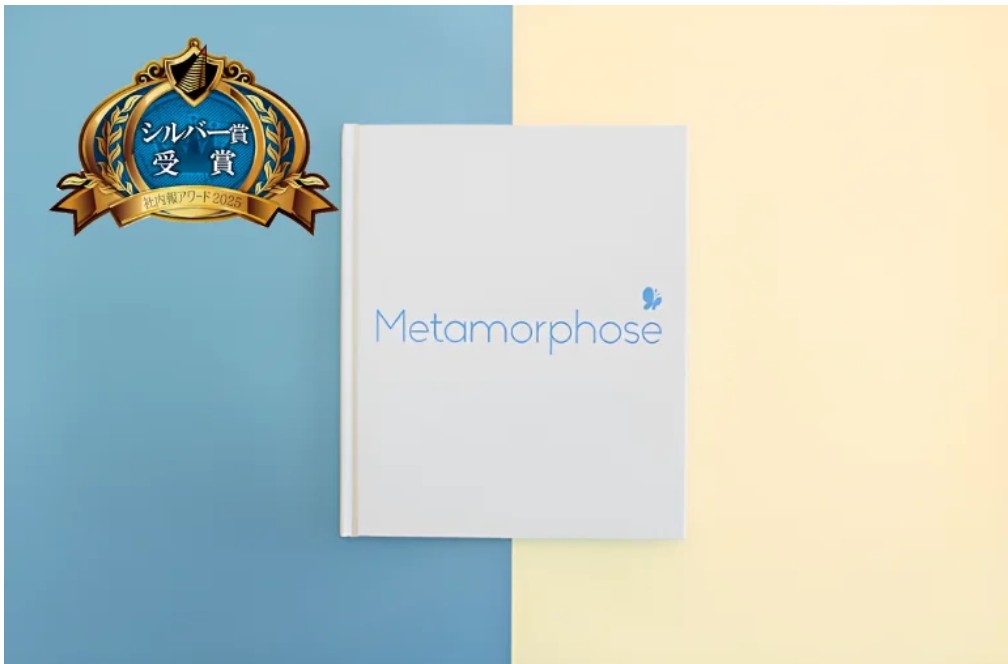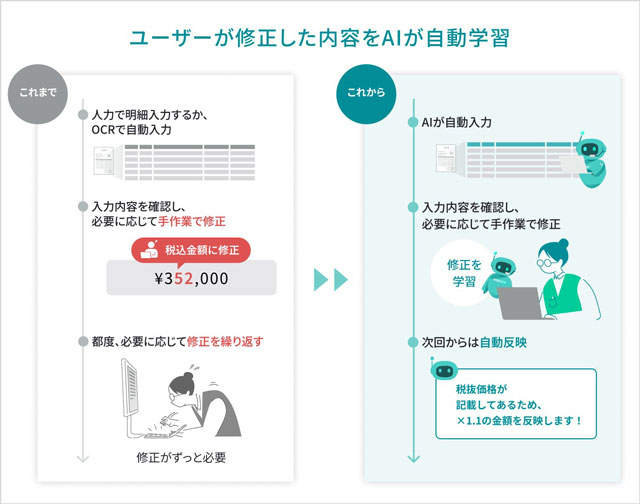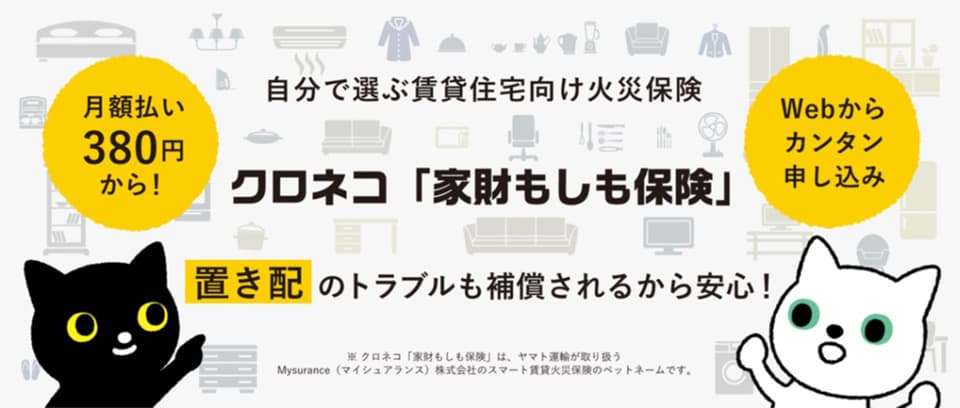10月19日、25年度宅地建物取引士資格試験が実施される。実施機関の不動産適正取引推進機構によると、今回の申し込み受け付け人数は30万6100人(速報値)で、前年度を1.6%上回り、2年連続で30万人を超えた。宅建士という資格、人材に対する社会的ニーズの更なる高まりを如実に示す結果である。実際に近年は、空き家や・空き地への対応、不動産コンサルティングによる物件の有効活用、賃貸管理や居住支援における広範な連携など、不動産事業者に対する行政や社会からの期待感は年々上昇している様子だ。
ただし、資格試験の受験者総数が多く、活躍の場も多いからといって、業界自体の未来が常に明るいと断言できるものでもない。同機構の集計では、24年度宅建試験の職業別合格者割合で、不動産業は最多とはいえ30.6%に過ぎなかった。以下は金融業、建設業と続き、それらを含む他業種の合計で約半数を占める。「学生」「その他」も各1割程度いるが、この比率に近年大きな変動はなく、不動産業の合格者は例年3割程度だ。そして、この比率が今後も変わらず続く保証はない。
つまり、宅建士への社会的ニーズ拡大が、そのまま不動産業界の活性化を意味するものではない。業界の魅力が乏しければ、宅建士人材の他業界への流出が拡大しかねない。免許と仕事があっても、肝心の宅建士が不足しては、業界の持続的な発展は見込めまい。〝人手不足〟が叫ばれる時代、業界は宅建士人材の流出に一層の警戒心を持つ必要があるはずだ。
そして、不動産業の魅力向上における最も大きな課題の一つは、不動産業に対する国民の根強い不信感ではないだろうか。全国宅地建物取引業協会連合会が毎年行っている意識調査「住宅居住白書」の25年版によると、「不動産店に対するイメージ」は「(とても、どちらかといえば)良い」は計30.0%で0.7ポイント減、「(同)悪い」は21.8%で0.7ポイント増。「良い」が「悪い」を上回ってはいるものの、マイナスイメージの解消に至る様子は見られない。
悪印象の理由は様々な要因が想定されるものの、根底にあるのは事業者に対する不信感であろう。実態として、宅建士資格がモラル面での信頼の象徴となるのは、現状はまだ少々厳しいようだ。宅建士を志す動機は、自身のキャリアや待遇を考えてのことが第一だろう。しかしそこで立ち止まっていては、少なくとも業界の信頼度向上や発展には結びつかず、自身の成長も頭打ちになるはずだ。信頼とは、誠実な行動の積み重ねの先にある。
受験者に限らず宅建業従事者は、顧客に誠実に向き合い地域に貢献することの重要性を、毎年の宅建士試験を機に改めて意識してはどうか。キャリアと共に信頼を築き、不動産業全体の信用にもつなげて、業界の更なる活性化と自身の成長を実現してもらいたい。