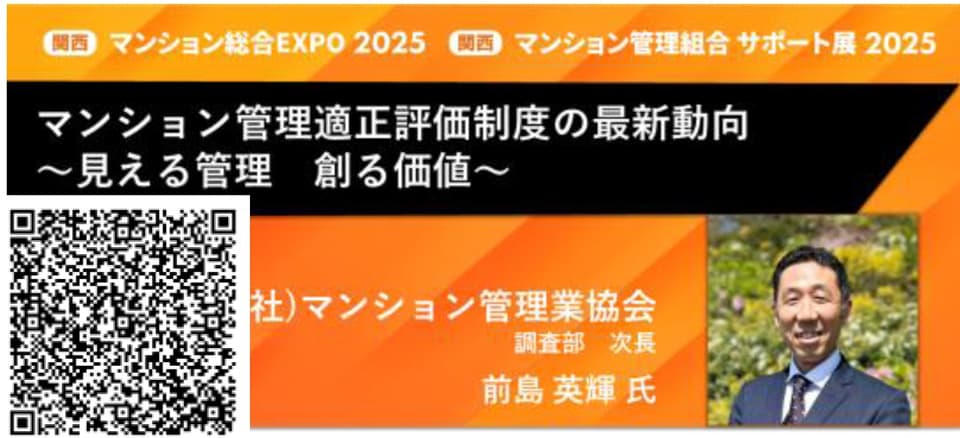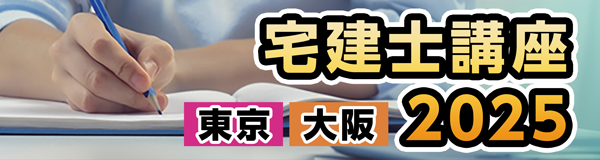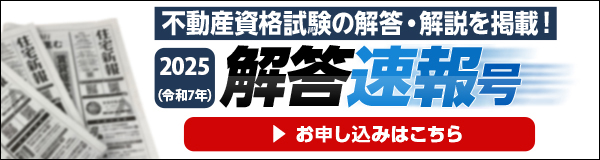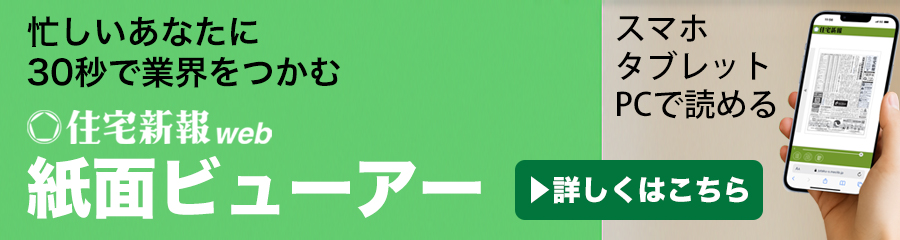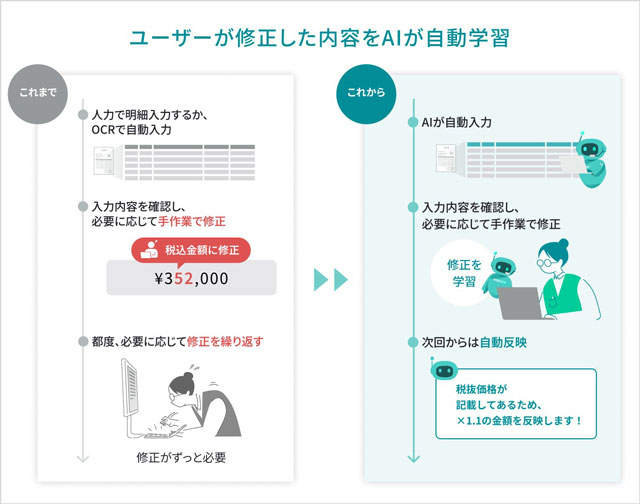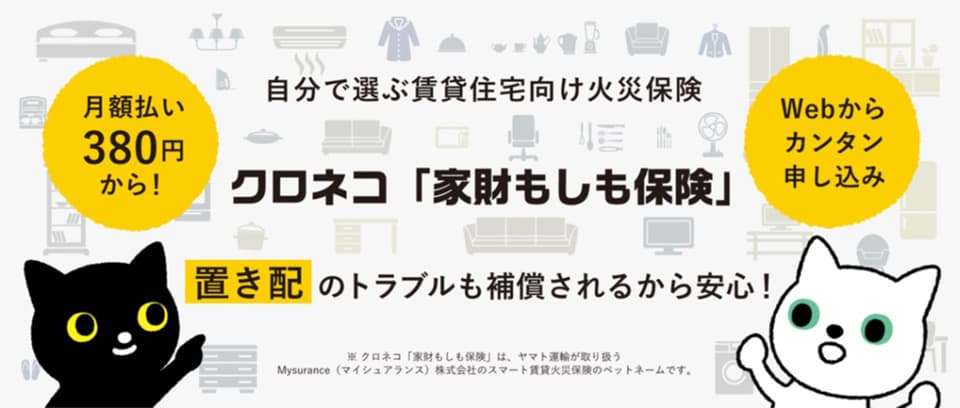今週から新年度となる。賃貸住宅市場の繁忙期も一段落というところだろうが、気になるのが更新時における継続中の入居者に対する家賃値上げ請求が多くなってきていることだ。世界的なインフレの進行による資材価格の高騰やエネルギーコストの上昇、さらにはマンション管理業務に従事する社員の人件費増加などを理由としたものだが、その値上げ幅を最小限にとどめる努力を期待する。
もちろん、値上げは入居者との交渉によって行われるものなので、必ずしも管理者側の意向が実現するとは限らないが、問題はその交渉の仕方が高圧的であってはならないということだ。ましてや、本当の狙いが値上げ交渉ではなく、法外な値上げを要求し、応じられない入居者を退去させ、より高い家賃で新たな入居者を募集することにあるのだとすればそれは論外というべきであろう。
管理会社からは事前にオーナーに対し、値上げ交渉に入ることの許諾を求める連絡があるはずなので、値上げ幅を確認すると共にオーナーとして値上げを希望しない場合にはその意思を明確に伝えることが肝要である。
◇ ◇
賃貸業と管理業は不動産業の原点である。全宅連不動産総合研究所発行の『不動産業沿革史』によれば、その始まりは江戸時代にまでさかのぼる。当時の長屋はそれぞれの大家の名を冠して例えば「作兵衛店」(さくべいだな)などと呼ばれていた。
同書によれば、業としての仲介業が発生したのは明治の中・後期ごろで、町内の有力者、世話役、家作差配人などが他人からの依頼で住む場所の世話をしているうちにそれが次第に職業化していったという。また、職業のあっせんをしていた口入屋(くちいれや)が副業として土地売買や貸家賃貸借のあっせんもするようになり〝二枚監察〟を得たのが始まりという説もある。
いずれにしても、賃貸業や管理業はそうした庶民の生活に密着し、大事な生活基盤を支える職業であったし、そこは基本的に今も変わっていない。それどころか一人暮らしが全世帯の40%を超え、その中には〝住宅弱者〟と呼ばれる人たちも多い今日、賃貸住宅市場の社会的役割は大きくなる一方だ。
職業の存在意義
住宅という国民の生活基盤に係わる不動産業は、社会に貢献してこそその存在意義があると考える。ちなみに、本紙『住宅新報』の創業者である故・中野周治氏は1971(昭和46)年に著した著書『不動産業と倫理』(住宅新報社刊)のまえがきにこう記している。
「われわれは、不動産業という特定業界から広く眼を社会全体に転じ、大所高所から業界を再認識することにより、はじめて不動産業者の社会的存在と責務を見極めることができる。またそのような自覚の上に立っての意思決定であってはじめて、企業活動を正しい方向に発展せしめることができるであろう」
◇ ◇
賃貸住宅は4月、実家を出て初めて一人暮らしをすることになった若い人たちが人生で最初にお世話になる不動産であり、住まいを生活基盤として意識する第一歩となる。その後も結婚や出産、子育てなど社会人としての前半を過ごすである。子供が成長したとき、〝我が家〟として想いを深くするのは賃貸住宅かもしれない。
かつて、賃貸住宅がマイホームを持つまでの〝仮住まい〟と考えられた時代もあったが、それは短絡的にマイホームを人生の大きな目標と考える大人が多かったからだ。しかし、今は人生の長寿化と日本経済の成熟化を背景に誰もが人生の先行きに不安を感じるようになった。住まいの選択も多様化せざるを得なくなった。だから今こそ、賃貸事業者は庶民の最も身近にあって住まいの相談が気軽にできる相手として生まれ変わらなければならない。
不動産業の原点である誇りを胸に――。