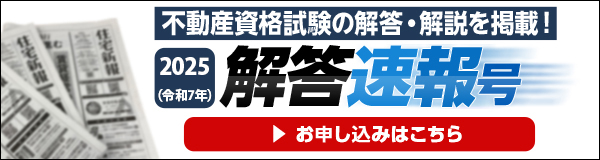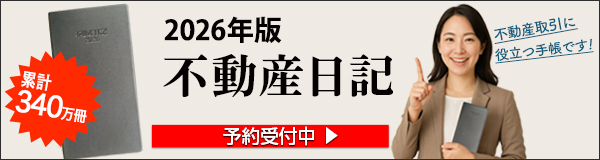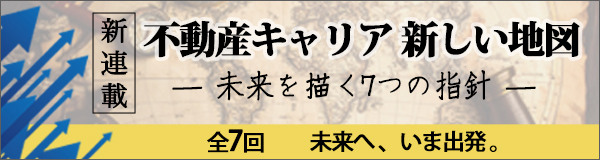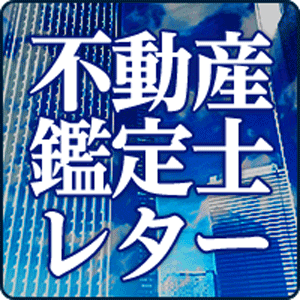わが家(千葉県船橋市)は旧日本住宅公団が土地分譲した高根台団地の中にあるが、現在そのわが家から歩いて1分程の圏内に空き屋が3軒ある。1軒は隣家で、あとの2軒はすぐ近くの角を曲がって20メートルほど行った道の両側にある。先日、そのうちの一軒の車庫のシャッターが錆びていて、剥がれた部分が道に飛び出していたため、老生危なく転ぶところだった。老いてからの転倒は大けがになりやすい。足でも骨折すれば長期入院を余儀なくされ、入院中に認知症になることもある。
◎ ◎ ◎
認知症といえば、筆者の知り合いが認知症と診断されていた母親の介護を事情があって弟一家から引き継いだと聞いていたが、先日ある会合で会ったとき「母が次第に元気になって、要介護度も下がりました」と嬉しそうに報告してくれた。そういう例も稀にあることは知っていたが、現実の話として聞いたのは初めてだ。
良かったと思うと同時に、認知症は本当に病気なのだろうかという日頃の疑問を強くした。もちろん、幻覚や妄想、徘徊、暴力など深刻な状態に陥るケースもあるが、昔なら「とうとう爺ちゃんもボケが始まったか」で済ましていた類のものも、今では認知症と判断されているのかなとも思う。
認知症と診断されても、症状が回復に向かうケースというのは早期発見が絶対条件とされている。認知症の中にも早く治療を始めれば治るタイプのものがある。たとえば、脳しゅようや脳脊髄液が脳内に異常にたまってしまう正常圧水頭症、あるいは頭を軽くなにかにぶつけたあと、しばらくたってから脳と硬膜の間に血液がたまる慢性硬膜下血腫などが原因の認知症は脳外科的処置で劇的に良くなる場合がある。
また、甲状腺ホルモンの異常が原因なら内科的治療で良くなることもある。筆者の知り合いのケースは、特に目立った治療をしなくても家族の親身な介護が症状の進行を止め、少しずつ回復に向かう〝認知症〟もあるということではないだろうか。
では、その絶対必要条件である早期発見ができるのは誰だろうか。言うまでもなく毎日一緒にいる家族である。
もちろん本人が「なんか、ヘンだぞ」と家族よりも早く気付くことはあるようだ。しかし、その本人が自ら病院に行って診断を受けるということはまずないらしい。だから家族が身近にいて、小さな変化も見逃さないことが大事になる。例えば「みそ汁の味が変わった」とか「最近、何を食べてもうまくない」とか言い出したら要注意だ。昼食を食べたあとで、「昼飯はまだ?」などと言い出したらかなり深刻だ。
◎ ◎ ◎
家族は一緒に住んでこそ〝家族〟といえる。認知症患者が増えている大きな要因は独居老人が増えているからだ。25年前の2015年に625万人だった高齢者の単身世帯が40年には896万人に増加する見込みだ。50年には1084万世帯となり、ようやくピークを迎える。50年には全世帯の44%が単身世帯でそのうちの46%が高齢者(65以上歳)だ。なんという荒涼とした風景か。
家はもともと家族にとっての幸福の象徴だ。だから、一生懸命ローンを払い続ける。空き家になっても家は家族が幸せに過ごした神聖な場所である。だから、誰も住まなくなってもそう簡単にそれを解体する気にはなれない。そのメンタリティーが日本で空き家が増えている哀しい要因である。
◇ ◇
春から夏に向かい始めた今、公園の新緑が美しい。シャッターが錆びた空き家は子供たちが遊びまわるその公園に面している。おそらくその空き家も何十年も前には両親と子供たちが住んでいて、公園に面していることを喜んでいたのではないだろうか。そういえば、1カ月程前に中年の男性が一人で庭の雑草を刈っている光景を見たことがあった――。